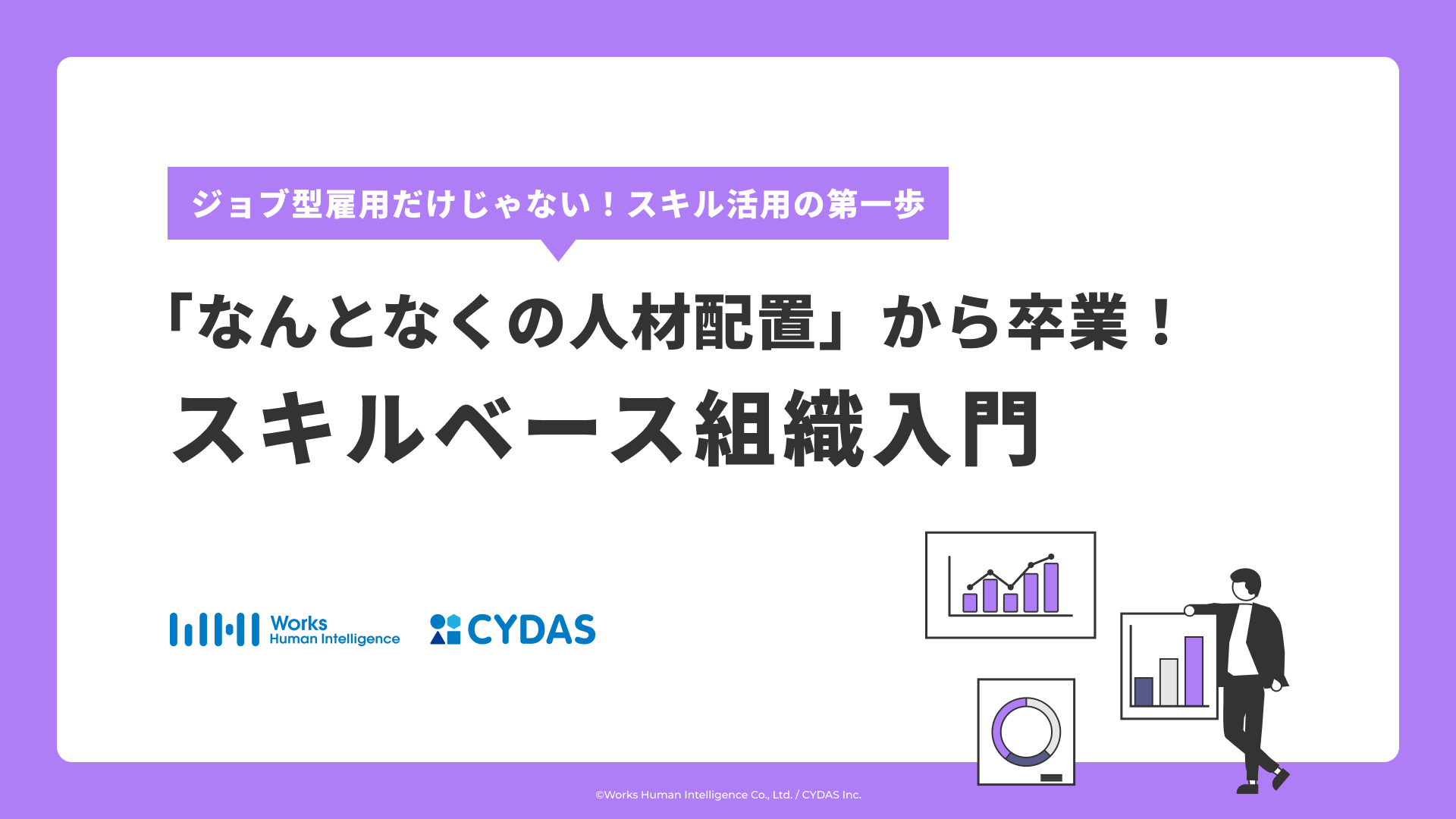2025.8.5
2025年人事トレンドワード【スキルベース・リベンジ離職・生成AI】を徹底解説
こんにちは!働きがいを応援するメディア「ピポラボ」を運営するサイダス編集部です。
近年、企業の人材戦略は急速に変化しており、2025年もその流れが加速し続けると予想されています。本記事では、2025年の人事トレンドとして注目される3つのキーワードを取り上げ、その特徴と、それぞれにおけるタレントマネジメントシステムの活用法をご紹介します。

【ピポラボ 30秒で解説! | 3つの2025年人事トレンドワードについて 】
- スキルベースの人材マネジメント
従来の職務・役職に基づくマネジメントではなく、従業員が持つスキルや能力を軸にしたマネジメント手法。職務を作業レベルまで細分化し、専門的な知識や技術だけでなくソフトスキルも考慮し人材を配置する。
- リベンジ離職
リベンジ退職とは、職場に不満を抱えた従業員が退職する際に、意図的に元の職場にダメージを与えることを意味する。
例)繁忙期の急な退職 / 競合企業へのノウハウ流出 / SNSでの内部情報漏えい など
- 生成AI
ディープラーニング(深層学習)によって自ら学習を重ね、人間が与えていない情報やデータもインプットし、テキスト、画像、音声、動画などの新しいコンテンツを生み出す技術。
スキルベースの人材マネジメント

スキルベースの人材マネジメントとは、従来の職務・役職に基づくマネジメントではなく、従業員が持つスキルや能力を軸にしたマネジメント手法のことです。欧米では一部の企業で、スキルデータを活用して採用・配置・育成・評価などの人材マネジメントを行う「スキルベース組織」の導入が始まっています。
日本では2020年以降、従来のメンバーシップ型雇用からジョブ型雇用へ移行する企業が増えてきましたが、ジョブ型雇用が特定の職務(ジョブ)に基づく雇用形態であるのに対し、スキルベース組織では個人のスキルに基づいて人材をマッチングするのが特徴です。スキルベース組織では、職務を作業レベルまで細分化して、専門的な知識や技術だけでなくコミュニケーション能力や課題解決能力といったソフトスキルも考慮し人材を配置します。そのため、職務が固定されるジョブ型雇用と比べると、プロジェクトや業務の変化に応じて柔軟に人材を活用できるメリットがあります。スキルベース組織は、ジョブ型雇用の発展形ではなく、変化が激しいビジネス環境に対応するためのまったく異なるアプローチであるといえるでしょう。
▼ スキルベース組織に興味のある方は必見です ▼
スキルベースの人材マネジメントを推進するには、従業員一人ひとりのスキルの可視化や開発支援が必要不可ですから、そのためにはスキルマップの作成や学習管理システム(LMS)との連携が重要になります。サイダスの「COMPANY Talent Management」シリーズでは、新入社員のオンボーディングやスキル習得状況を把握できる「ファンダメンタルCDP」機能や、スキルチェックを行える「プロフェッショナルCDP」機能を提供しています。特に「プロフェッショナルCDP」機能は、LMSと連携してそれぞれのスキルチェックの結果に応じた学習コンテンツをレコメンドすることで、従業員の自律的なスキル習得をサポートします。
リベンジ離職
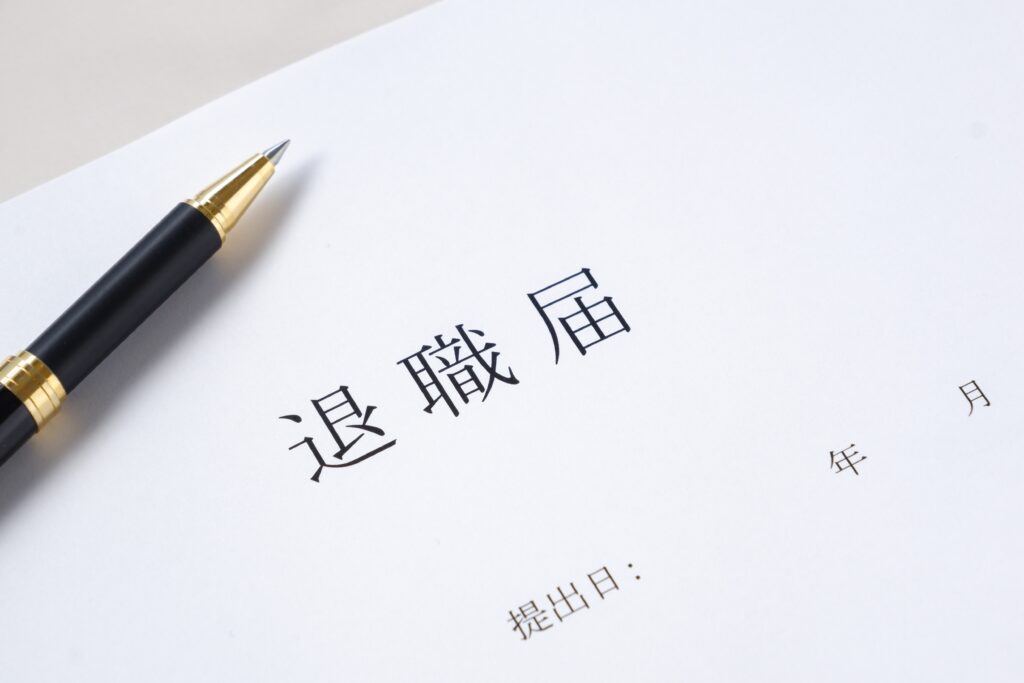
リベンジ退職とは、職場に不満を抱えた従業員が退職する際に、意図的に元の職場にダメージを与えることを指します。例えば、繁忙期の急な退職や、競合企業へのノウハウ流出、SNSでの内部情報漏えいなどがそれにあたります。
厚生労働省の調査(※)によると、転職入職者が前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」と答えている割合が、男性は9.1パーセント、女性は13.0パーセントに上り、職場における心理的安全性の欠如や従業員エンゲージメントの低下が、リベンジ退職の要因のひとつになっていると考えられます。
リベンジ退職を防ぐためには、従業員の離職予兆を早期に発見し、エンゲージメント向上施策を講じることが大切です。「COMPANY Talent Management」シリーズの「9box」機能では、分析の目的に合わせて任意の縦軸・横軸を設定し、人材をマッピングすることができます。例えば、適性検査「CUBIC」の人間関係満足度と職場満足度を両軸に設定することで、人間関係と職場満足度がともに低い従業員を早期に発見することができます。
フォローが必要な人材を見つけたら、定期的に1on1ミーティングを実施し、業務に関する不満や人間関係における悩みを抱えていないか、丁寧に対話を重ねていきましょう。「COMPANY Talent Management」シリーズの「1on1 Talk」機能を活用すれば、日々の面談記録や振り返りを蓄積でき、それぞれの心身の健康状態も記録できるため、従業員一人ひとりのコンディションの変化にも気づきやすくなります。
※参照:厚生労働省 「令和5年雇用動向調査結果の概況 」
生成AIの活用

昨年に引き続き、2025年もあらゆる分野で生成AIの活用が注目されています。生成AIとは、学習したデータを基に新しいデータや情報を生成する人工知能(AI)で、「ジェネレーティブAI」と呼ばれることもあります。従来のAIの主な機能とは、人間が与えた学習データに基づいて、その情報の中から適切な回答を導いたり結果を予測したりするといったことを、あらかじめ決められた範囲内で自動的に行うことでした。
一方、生成AIはディープラーニング(深層学習)によってAIが自ら学習を重ね、人間が与えていない情報やデータもインプットして、テキスト、画像、音声、動画などの新しいコンテンツを生み出すことができます。
▼「生成AI」についてさらに詳しく知りたい方はこちらもご覧ください! ▼
生成AIとは?種類と使い方、しくみとメリットデメリットを分かりやすく解説
AI技術の進化により、人事領域におけるデータ活用もさらに高度化することが予測され、タレントマネジメントシステム領域においてもAIや生成AIを活用した機能の開発が進められています。例えば、評価情報や面談記録、キャリア申告、スキル情報など、システムに蓄積された人材データを基に特定のプロジェクトに最適な人材を抽出する機能や、従業員一人ひとりのプロフィールを自動で要約することができる機能が登場しています。
一方で、システム内にあるデータの整備が不十分だと適切な結果を導くことができないこともあるため、機能を適切に活用するためには定期的にメンテナンスを行うことがおすすめです。
なお、「COMPANY Talent Management」シリーズでは、AIや生成AIの技術を取り入れた機能を、順次リリース予定です。
さいごに
2025年、そしてその先の未来を見据え、企業の人材戦略は常に進化が求められます。今回ご紹介したトレンドワードが、皆さんの組織における『働きがい』の向上と持続的な成長のヒントとなれば幸いです。
ピポラボは、これからも人事の皆さんがより良い人材戦略を構築できるよう、実践的なヒントと最新の情報をお届けしてまいります。