2025.3.26
データドリブン人事とは?意味や導入方法、タレントマネジメントシステムとの関係性を解説
こんにちは!働きがいを応援するメディア「ピポラボ」を運営するサイダス編集部です。
今回のテーマは、「データドリブン人事」です。近年、タレントマネジメントシステムやサーベイツール等の普及に伴い、「データドリブン」という言葉をよく耳にするようになりました。しかし、「なんとなく重要そうだけど、具体的にはどういうこと?」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、データドリブン人事の定義から始まり、注目される理由や導入のメリット、タレントマネジメントシステムとの関連性まで、包括的に解説します。人事担当者の皆様が、データを活用して組織の成功に貢献するためのバイブルとして、ぜひご活用ください。

目次
データドリブン人事とは

データドリブン人事とは、収集したデータに基づいて意思決定を行う人事管理手法であり、「データドリブンHR」と言われることもあります。従来の経験や勘に頼ったアプローチとは異なり、客観的なデータ分析を活用して人材の最適配置や育成計画を策定し、組織のパフォーマンス向上を図ります。
従来の人事管理では、主に直感や過去の経験に基づいて人材の評価や配置が行われていました。しかし、データドリブン人事では、適性検査、組織サーベイ、人事評価等の大量の人事データを活用することで、より精度の高い意思決定を行います。これにより、従業員のパフォーマンス向上や離職率の低下といった具体的な成果が期待できます。
データドリブンとは
データドリブン(Data Driven)とは、直訳すると「データ駆動型」という意味で、感情や経験や勘に頼るのではなく、収集したデータを基に意思決定を行うアプローチのことを指します。この手法を用いることで、客観的なデータに基づいた判断が可能となり、組織の目標達成に向けた効果的な戦略策定に繋がります。
一方、データドリブンの対極にあるのが「KKD」です。「KKD」とは、「勘・経験・度胸」の頭文字をとったもので、データに基づいた意思決定ではなく、経験や勘、直感といった主観的な判断に基づいて行動することを指します。
たとえば、飲食店で新しいメニューを開発する場合を考えてみましょう。シェフやスタッフの経験値や直感、トレンド感覚を基にメニューを考案するのは、KKD的なアプローチです。一方で、売上データや顧客の注文履歴、アンケートの結果等の客観的な情報を活用してメニューを開発するのが、データドリブン的なアプローチといえます
もともとデータドリブンは、マーケティング分野でよく使われていた用語ですが、ITツールやクラウドシステムの普及により、経営や人事の領域でも活用されるようになりました。
データドリブン人事で扱うデータ例
データドリブン人事で活用できる人材データには、以下のようなものがあります。取得すべきデータは、企業の課題や目的によって異なるため、自社にとって何が必要になるかを見極めることが大切です。
- 従業員属性データ:年齢、性別、経験、スキル、資格、評価等
- 勤怠データ:勤務時間、残業時間、休暇取得状況等
- 評価データ:人事評価、目標達成度、360度評価等
- 教育データ: 研修受講履歴、資格取得状況等
- エンゲージメントデータ:従業員満足度調査、離職率等
これらのデータを分析することで、従業員の行動パターンや組織全体の傾向を把握し、より効果的な人事戦略を立てることが可能になります。
これらのデータを一元管理するには、「COMPANY Talent Management」シリーズの活用がおすすめです。
データドリブン人事が注目される理由
データドリブン人事が注目される理由には、大きく分けて「価値観の多様化による人材流動化の高まり」「データ分析技術の進化」「市場トレンドへの適応」の3つの側面から説明できます。
価値観の多様化による人材の流動化の高まり
従来の日本では、終身雇用を前提に、年功序列で人材を評価する傾向が強かったと言えます。しかし、近年では転職が一般化し、個人が自身のキャリアを主体的に考え、能力や成果に応じて報酬を求める価値観が広まっています。人材の流動化が高まっている現代において、優秀な人材を確保し、育成・定着させることは企業にとって重要な課題です。
このような価値観の変化や人材の流動化に伴い、企業は、経験や勘に基づいた従来の評価や異動配置ではなく、個人の能力や成果を可視化し、客観的に判断できるデータドリブン人事の必要性を認識し始めています。従業員のエンゲージメントやモチベーション、離職リスク等を分析することで、従業員一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかな人材マネジメントが可能になります。
データ分析技術の進化
AIや機械学習等によるデータ分析の技術が向上し、人事分野においても、膨大な人事データを高速かつ高精度に分析することができるようになりました。たとえば、タレントマネジメントシステム等に蓄積されたデータを基に、従業員の潜在能力や今後のパフォーマンスを予測する等、従来は困難であった分析が可能となり、より精度の高い人材配置や人材育成、採用活動が実現できるようになっています。
市場トレンドへの適応
市場のトレンドや業界の動向もデータドリブン人事の普及に大きな影響を与えています。DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展に伴い、データ活用の重要性がますます高まっており、人事部門もこの流れに適応することが求められています。企業が競争優位性を確立し、成長し続けるためには、人事戦略のデータ活用が欠かせません。
データドリブン人事は、企業の成長を力強く後押しする手法として、今後もますます注目を集めていくと考えられます。
データドリブン人事を推進するメリット

データドリブン人事を推進することで、企業は従来の人事管理では得られなかった様々なメリットを享受できます。大きく分けて、組織全体へのメリット、従業員へのメリット、人事部門へのメリットの3つの視点から整理できます。
組織全体へのメリット
1.企業競争力の強化
データに基づいた客観的な人事戦略は、最適な人材配置や育成を実現し、結果として企業全体の生産性向上、業績向上に貢献します。
2.戦略的人事の実現
データドリブン人事を通して、経営戦略と連動した人材戦略を立案・実行することが可能になります。
3.コスト削減
採用活動の効率化や離職率の低下による採用・教育コストの削減、適切な人員配置による人材不足の解消等が期待できます。
従業員へのメリット
1.従業員エンゲージメントの向上
働きがいのある環境作りや、従業員の能力・個性に合わせた最適な評価・育成・配置は、従業員のモチベーションや満足度向上に繋がり、エンゲージメント向上に貢献します。
2.キャリア開発の促進
データに基づいた客観的な評価やフィードバックは、従業員の成長を促進し、キャリア目標の達成を支援します。
人事部門へのメリット
1.人事部門の業務効率化
データ分析の自動化や可視化ツール導入により、人事担当者はより戦略的な業務に集中できます。
2.人事評価の公平性・透明性向上
データに基づいた客観的な評価は、評価のばらつきを抑え、従業員の納得感を高めます。
3.説得力のある意思決定
データに基づいた根拠のある説明は、経営層や現場上司への提案をスムーズにし、円滑なコミュニケーションを促進します。
データドリブン人事を推進するための4つのステップ

データドリブン人事を効果的に推進するためには、「人材データの収集」「人材データの可視化」「人材データの分析」「アクションプランの策定」という4つのステップが重要です。これらのステップを順に実行することで、組織は人事データを最大限に活用し、戦略的な意思決定を行うことが可能になります。それぞれ詳しく解説します。
STEP1:必要な人材データの種類や項目を特定する
データドリブン人事を推進する最初のステップは、必要な人材データの種類と項目を特定することです。人材データの棚卸しを行い、現状でどのようなデータが取得できているか、組織の目標や人事戦略の達成のためには何が不足しているかを把握しましょう。
【具体例】
従業員エンゲージメントの向上を目的とする場合:
従業員満足度調査の結果や、従業員間のコミュニケーション頻度、離職率等のデータが考えられます。
採用活動の効率化を目的とする場合:
応募者数、採用コスト、採用後のパフォーマンス等のデータが必要です。
これらのデータは、人事システムや勤怠管理システム、給与システム等に散在していることが多く、必要なデータを一元管理できる体制を構築することが重要です。様々な人材データを一元管理するなら、タレントマネジメントシステムの導入がおすすめです。
STEP2:必要な人材データを収集・可視化する
続いて、STEP1で特定した必要なデータを収集し、視覚的にわかりやすい形に整理します。人材データは、複数のシステムやフォーマットに分散していることが多いため、統一的に管理できるしくみを整えましょう。また、データを収集する際には、定期的に更新し、リアルタイムで活用できる状態に保つことが重要です。
【可視化の例】
- 従業員満足度調査の結果をレーダーチャートで表示し、部署や年代ごとの傾向を比較
- 採用プロセスの各フェーズごとの応募者数や通過率をグラフ化
- 離職率の推移を年度別・部門別に比較し、改善点を特定
効果的な可視化ツールや手法としては、タレントマネジメントシステムの導入やBIツールやダッシュボードの活用が挙げられます。タレントマネジメントシステムの基本について知りたい方は、下記の資料も無料でダウンロードできるのでぜひ参考にしてください。
STEP3:人材データを分析する
STEP2で収集・可視化したデータを基に、組織の課題や強みを分析します。データ分析によって、従業員のエンゲージメントやパフォーマンスに影響を与える要因を明確にし、具体的な施策に繋げることが可能になります。
【分析例】
離職率分析
- 部署別、年齢別、勤続年数別等の属性ごとに離職率を集計し、傾向を分析
- 離職理由に関するデータを分析し、退職の要因を特定
- 従業員満足度調査の結果と離職率の相関関係を分析し、離職の予兆を把握
ハイパフォーマー分析
- ハイパフォーマーと他の従業員のパフォーマンスデータを比較分析し、特徴を抽出
- ハイパフォーマーの行動特性やスキルを分析し、育成に活用できる指標を開発
- 採用活動において、ハイパフォーマーの獲得に繋がる指標を特定
STEP4:アクションプランを策定する
STEP3のデータ分析の結果を基に、具体的な施策を策定・実行します。ここでは、得られた知見を活かし、組織の目標達成に繋がる施策を設計することが求められます。
たとえば、離職率が高い場合には、ワークライフバランスを改善する施策を導入したり、採用基準を見直し、より適性の高い人材を確保することで、組織のパフォーマンス向上を図ることができます。
また、アクションプランの効果を測定するために、KPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的に進捗を確認することが重要です。
【アクションプランの例】
- 離職率改善のためのワークライフバランス施策の導入
- ハイパフォーマーの育成プログラムの開発
- 採用プロセスの見直しによる適切な候補者の選定
データ分析から得られたインサイトを基に、具体的なアクションプランを策定することは、データドリブン人事の成功に欠かせません。まず、分析結果を詳細に検討し、組織の目標達成に向けた具体的な施策を明確化します。
アクションプランを実行に移す際には、各施策の担当者の設定や進捗管理の方法のすり合わせ、実行後の効果検証も忘れずに行いましょう。これら4つのプロセスを継続的に実施することで、データドリブン人事の取り組みが効果的に機能し、組織全体の目標達成に寄与します。
データドリブン人事を成功させるポイント
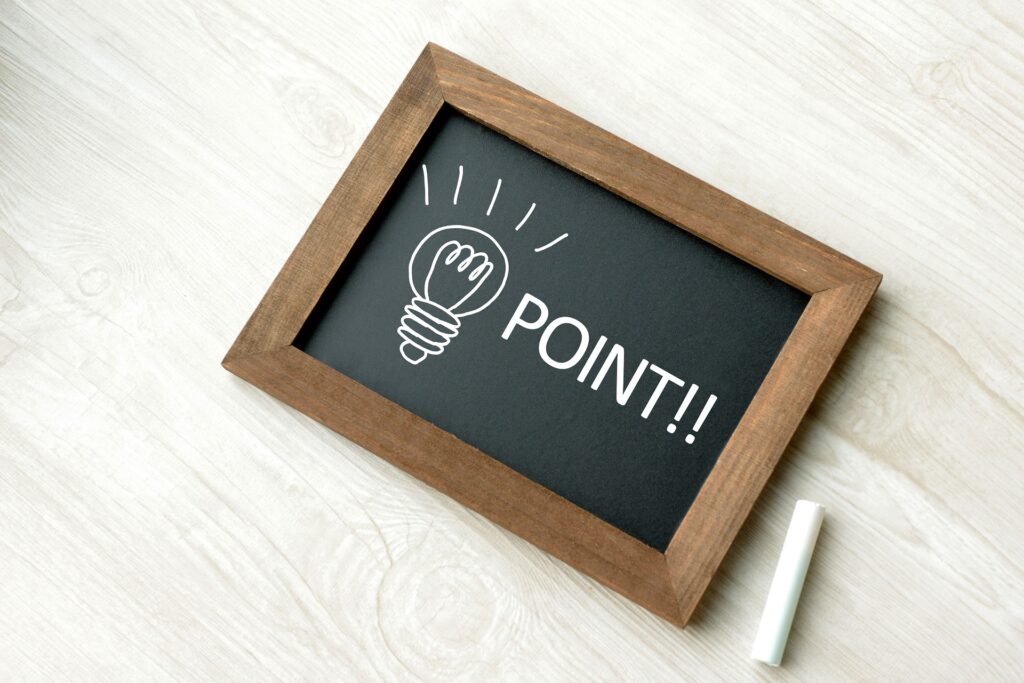
データドリブン人事を成功させるポイントは、以下の3つです。
データに基づく意思決定の重要性を啓蒙する
データドリブン人事を推進する上で、組織全体でデータに基づいた意思決定を行うことの重要性を理解し、共有することが不可欠です。そのためには、経営層から現場レベルまで、データの重要性や活用方法を理解するための研修やワークショップ等を実施し、データドリブン文化を根付かせましょう。 部署ごとにKPIを設定し、データに基づいた進捗管理や評価を行うことで、データ活用の効果を実感できる機会を増やすことも有効です。
データ分析に強い人材を確保する
データドリブン人事を推進するためには、人事データの収集、分析、解釈、活用等、専門的な知識やスキルを持った人材が必要です。 特に、統計学やデータ分析ツールを使いこなせる人材や、人事制度や組織に関する知識を有し、分析結果を人事戦略に落とし込める人材が求められます。
社内に専門人材が不足している場合は、外部の専門家やコンサルタントの力を借りることも有効ですが、同時に、従業員のデータ分析スキル向上のための研修制度を導入したり、データ分析に特化したチームを新設したりする等、中長期的な視点での人材育成も重要です。
データの質と信頼性を確保する
データドリブン人事の成否は、データの質と信頼性にかかっています。分析に使用するデータが正確でなければ、誤った結論を導き、効果的な人事戦略を策定できません。 データの収集方法を標準化し、入力ミスや漏れを防ぐとともに、定期的なデータクレンジングを行い、データの品質を維持する必要があります。
また、個人情報保護の観点から、データの取り扱いに関するルールを明確化し、適切なセキュリティ対策を講じることも重要です。 従業員に対して、データの利用目的や方法を透明化し、安心してデータを提供できる環境を構築する必要があります。
データドリブン人事を推進する鍵はタレントマネジメントシステム
データドリブン人事を効果的に推進するためのツールとして、近年タレントマネジメントシステムが注目されています。タレントマネジメントシステムとは、従業員に関する情報を一元管理し、評価業務や人材育成・活用を効率的・効果的に行うためのツールです。従来の人材管理システムや人事評価システムで扱う情報に加え、個性や性格、キャリア希望等の従業員に関するあらゆるデータを集約します。
タレントマネジメントシステムを導入することで、下記のようにデータドリブン人事を推進することができます。
現状の可視化
従業員一人ひとりのスキルや経験、キャリアパス等を可視化することにより、組織全体の能力や課題を明確に把握することができます。ダッシュボード機能等を使えば、細かなデータ分析を行う必要もなく、直感的に今の組織の情報を把握することができるのもタレントマネジメントシステムの魅力の一つです。
データ分析による課題の発見
従業員のエンゲージメント、パフォーマンス、離職率等のデータを分析することで、潜在的な問題点を早期に発見できます。データを基に適切な対策を講じることで、従業員の定着率向上や生産性の向上に繋げられます。
戦略人事の実現
戦略人事とは、企業の経営戦略と人材マネジメントを密接に連携させ、人材を戦略的に活用することで、企業の成長や目標達成を図る人事の考え方またはその体制を意味します。
タレントマネジメントシステム上に蓄積された人材データを活用することで、サクセッションプラン(後継者育成計画)の策定や、最適な異動配置を検討することができます。
戦略的なタレントマネジメント運用なら
「COMPANY Talent Management」シリーズ

「COMPANY Talent Management」シリーズは、日本企業の高度で複雑な人事制度に最適化され、人的資本マネジメントを統合的にサポートするタレントマネジメントシステムです。組織ごとに異なる人事課題にスピーディに対応できる豊富な機能を備えており、組織力を強化するための分析や、育成のためのプラン作成等、多岐に渡る人材マネジメント運用がこのシステム一つで実現できます。
「3分でわかる!サービス・プランガイド」をいますぐ無料ダウンロード

