2025.6.13
エンゲージメントサーベイを行う目的とは?注目される理由やサーベイの種類を解説
こんにちは!働きがいを応援するメディア「ピポラボ」を運営するサイダス編集部です。
今回のテーマは、「エンゲージメントサーベイ」です。近年、組織全体の生産性向上のため、エンゲージメントサーベイに注目する企業が増えています。従業員の意識や働きがいを測るためのこの調査は、単なるアンケートではありません。では、エンゲージメントサーベイの真の目的とは一体何なのでしょうか。
本記事は、エンゲージメントサーベイを行う目的を中心に、エンゲージメントサーベイの種類や活用ポイントをお伝えします。

目次
エンゲージメントサーベイとは
エンゲージメントサーベイとは、従業員が自分の仕事や組織にどれだけ愛着・意欲・貢献意識を持っているかを数値化し、具体的に把握・改善するための調査ツールです。これは、従業員が自社にどれだけコミットしているかを測定し、組織全体のパフォーマンス向上に繋げるために活用されます。
エンゲージメントサーベイは定期的に実施し、従業員の声を直接反映させることで、企業文化や職場環境の改善に役立ちます。ただし、エンゲージメントサーベイを利用しても、勝手にエンゲージメントが高まるわけではありません。なぜなら、エンゲージメントサーベイはあくまで、組織の課題を可視化するための指標だからです。
大事なことは、明らかになった課題ときちんと向き合い、解決していくことです。エンゲージメントサーベイで見つけた特定の個人の課題を追求するのではなく、従業員と一緒に解決方法を検討し、働きやすい環境について考えることが大切になります。
そもそもエンゲージメントとは?
エンゲージメント(engagement)とは、「婚約」「誓約」「約束」を意味する単語で、ビジネス場面においてエンゲージメントは「職場(企業・団体)と従業員の関係性」や「自社と顧客の関係性」を表す際に用いられます。
たとえば「従業員のエンゲージメント向上」は、「従業員が自社に対しての愛着や貢献の気持ちや意志を深めること」という意味として使われます。
従業員エンゲージメントとは
従業員エンゲージメント(Employee Engagement)とは、従業員が「会社や仕事に対してどれだけ主体的に関わり、貢献したいと感じているか」という心理的な状態を指します。単なる「従業員満足度」や「働きやすさ」とは異なり、エンゲージメントはもっと能動的なものです。
たとえば、以下のような特徴があります。
【エンゲージメントが高い従業員は…】
- 自分の仕事に誇りを持っている
- 組織の目標達成に向けて自発的に動く
- 周囲に良い影響を与え、チームの成果にも貢献する
- 成長意欲が高く、変化や課題にも前向きに取り組む
【エンゲージメントが低い従業員は…】
- やらされ感が強く、仕事に熱意がない
- 離職リスクが高まる
- チームの士気を下げてしまうこともある
ワークエンゲージメントとは
ワークエンゲージメント(Work Engagement)は、仕事そのものに対してポジティブで活力に満ちた精神状態のことを指します。この概念は、オランダの心理学者ウィルマー・B・シャウフェリらによって提唱され、以下の3つの要素から構成されるとされています。
【3つの要素】
1. 活力(Vigor)
仕事にエネルギーを持って取り組み、疲れにくく意欲的である状態。「職場では、元気がでる」「仕事をしていると活力がみなぎるように感じる」などの特徴があります。
2. 熱意(Dedication)
仕事に誇りや意義を感じ、深く関わっている状態。「仕事に熱心である」「仕事は、私に活力を与えてくれる」などの特徴があります。
3. 没頭(Absorption)
仕事に夢中になり、時間を忘れるほど集中している状態。「仕事につい夢中になってしまう」「仕事中に幸せだと感じる」などの特徴があります。
エンゲージメントサーベイの主な目的
エンゲージメントサーベイは、従業員の声を収集し、組織の課題を明らかにするための有効な手段です。しかし、その目的は単なる「意見集め」ではありません。サーベイを実施する真の目的は、大きく以下の4つに集約されます。それぞれ詳しく解説します。
①組織の現状を「可視化」する
従業員の感じているモヤモヤや意欲、働きがいは、日常業務の中では見えにくいものです。エンゲージメントサーベイは、そうした感情や認識を数値化・定量化することで、現場と経営層の間にある見えないギャップを可視化します。
部署や職位ごとの傾向、時系列での変化、特定の要因による影響などを把握することで、客観的な組織診断が可能になります。
②離職・人材流出のリスクを早期に察知する
エンゲージメントの低下は、従業員の離職や不満の蓄積に繋がりやすくなります。サーベイは、従業員のモチベーションの低下や不信感の兆候を早期に発見し、「手遅れになる前の対処」を可能にします。特に、優秀な人材ほど職場環境やマネジメントへの感度が高く、エンゲージメントの低さを理由に離職を選びがちです。
企業からの一方的な人事評価だけでは、従業員が何を考えているのかまで理解を深めることはできません。また、従業員満足度を確認しても、それは単純に企業が与えた環境への満足度を測るに過ぎず、従業員本人の考え方や今のキャリアに対する悩み、指向性まではなかなか掴めないでしょう。
そのため、従業員を多角的に観察して情報収集をし、理解を深めるという目的でエンゲージメントサーベイを実施していく必要があります。サーベイを行った結果、従業員が考えていることと企業の望む方向とは異なることがあるかもしれません。「どのようなギャップが生まれているのか」「企業の伝えたいことがどこまで伝わっているのか」など、従業員に対する理解を深めることで、離職防止の対策を打ちやすくなります。
③組織改善・職場づくりの出発点となる
サーベイの目的は「測ること」ではなく、「改善に繋げること」です。従業員の声を拾い上げ、それをもとに組織風土・人間関係・業務環境などを見直すことで、従業員が本来持っている力を最大限に引き出す環境を整えることができます。これは、心理的安全性や多様性の尊重といった現代的なマネジメントにも直結します。
④マネジメント力の育成・支援
サーベイ結果は、各部門の管理職やリーダーのマネジメントの「鏡」にもなります。部下との関係性、フィードバックの質、目標の共有度などを知る手がかりとなり、現場のマネージャーがリーダーシップを高める機会となります。自部署のデータをもとに行動変容を促すことで、管理職の自覚と成長にも繋がります。
エンゲージメントサーベイが注目される理由
近年、エンゲージメントサーベイが注目されている理由は以下の通りです。
①働き方の多様化と従業員意識の変化
テレワーク、フレックス制度、副業など、働き方の自由度が増す中で、従業員は「どれだけ会社に貢献したいと思えるか」「仕事にやりがいを感じられるか」といった内面的な動機づけ(エンゲージメント)をより重視するようになっています。そのため、従来のように、給与や福利厚生といった外的要因だけでモチベーションを維持することは難しくなりつつあります。
このような背景から、従業員の内面的な繋がりや意欲を可視化するエンゲージメントサーベイの重要性が高まっています。
②離職リスクの高まりと人材流動化の加速
人材の流動化が進み、特に高スキル人材や若手の離職が企業にとって大きな課題となっています。退職理由として「上司との関係」「成長機会の不足」「組織への不信感」など、離職環境やエンゲージメントに関わる要因が多く挙げられます。
エンゲージメントサーベイは、こうしたリスクを早期に察知する手段として有効です。定量的なスコアをもとに、職場の課題を特定し、対策を講じることで、離職を未然に防ぐことができます。
離職防止には、1on1対策を行うこともおすすめです。ポイントを知りたい方はこちらのガイドブックもおすすめです。
③人的資本経営やESG経営
近年、企業の持続的な成長には「人的資本の可視化」が欠かせないとされており、エンゲージメントはその重要な指標の一つです。人的資本の情報開示(ISO 30414など)を求められる機会が増える中で、エンゲージメントスコアは、投資家や外部ステークホルダーに向けた重要なエビデンスとなります。
このような背景もあり、エンゲージメントサーベイを通じて、人的資本経営をデータで支える企業が増えています。
人材の流動化が進み、特に高スキル人材や若手の離職が企業にとって大きな課題となっています。退職理由として「上司との関係」「成長機会の不足」「組織への不信感」など、離職環境やエンゲージメントに関わる要因が多く挙げられます
エンゲージメントサーベイの種類
エンゲージメントサーベイには、目的や活用シーンに応じていくつかの種類があります。主に次の3つが代表的です。
①年次サーベイ(センサスサーベイ)
年に1回など、定期的に全社一斉で実施される大規模かつ網羅的なサーベイです。「センサス(Census)」とは「全数調査」の意味で、従業員全員を対象に行うことが特徴です。設問数も多く、組織の全体傾向や変化を把握しやすいため、中長期的な人事戦略や制度設計に役立ちます。
【特徴】
- 包括的な設問構成(20問〜100問程度)
- 対象範囲:全従業員
- 実施頻度:年1回または半年に1回
【メリット】
- 組織全体の傾向や構造的課題を把握できる
- 部門間比較や経年比較が可能
- 経営層の意思決定の根拠として活用しやすい
【デメリット】
- 実施から集計、分析、改善までに時間がかかる
- 状況の変化をリアルタイムには把握しづらい
②パルスサーベイ(短期・高頻度)
月次や四半期ごとなど、短いスパンで繰り返し実施するサーベイです。設問数を絞って簡易化することで、従業員の「今」の状態をタイムリーに把握するのに適しています。センサスサーベイの補完や、現場改善のツールとして活用されています。
【特徴】
- 設問:3〜10問程度/所要時間は数分などの簡易設計
- 対象範囲:全社または特定部門
- 実施頻度:月次、隔月、四半期など高頻度
【メリット】
- 状況変化や課題の兆しをリアルタイムで把握できる
- フィードバックや改善を素早く回せる
- 回答の負担が少なく、継続的な運用に向いている
【デメリット】
- 単発的な実施では効果が薄くなる
- 継続的な運用、改善体制が必要
③特化型サーベイ(テーマ別・対象別)
特定のテーマや対象に焦点を当てた目的特化型のサーベイです。エンゲージメントの中でも、特に注視したい領域を深掘りすることができます。マネジメント強化やハラスメント予防、オンボーディング効果の確認などにも活用されます。
【特徴】
- 設問数:テーマに応じて柔軟に設計
- 対象範囲:特定部門、職位、タイミングに限定
- 実施頻度:必要に応じて適宜実施
【メリット】
- 特定課題に対する深いインサイトが得られる
- 個別対策の効果測定が可能
- 他のサーベイと組み合わせて活用しやすい
【デメリット】
- 組織全体の状態は把握しにくい
- 設問設計に専門的な知見が求められる
エンゲージメントサーベイを行う際には、自社の分析目的に合った形式を採用することが大切です。近年では、センサスサーベイで組織全体の傾向を把握し、パルスサーベイで現場の変化に対応するといった、複数のサーベイを組み合わせる手法が主流になりつつあります。目的や課題に応じて適切な種類を選び、継続的な改善に繋げることが重要です。
エンゲージメント・サーベイの活用ポイント
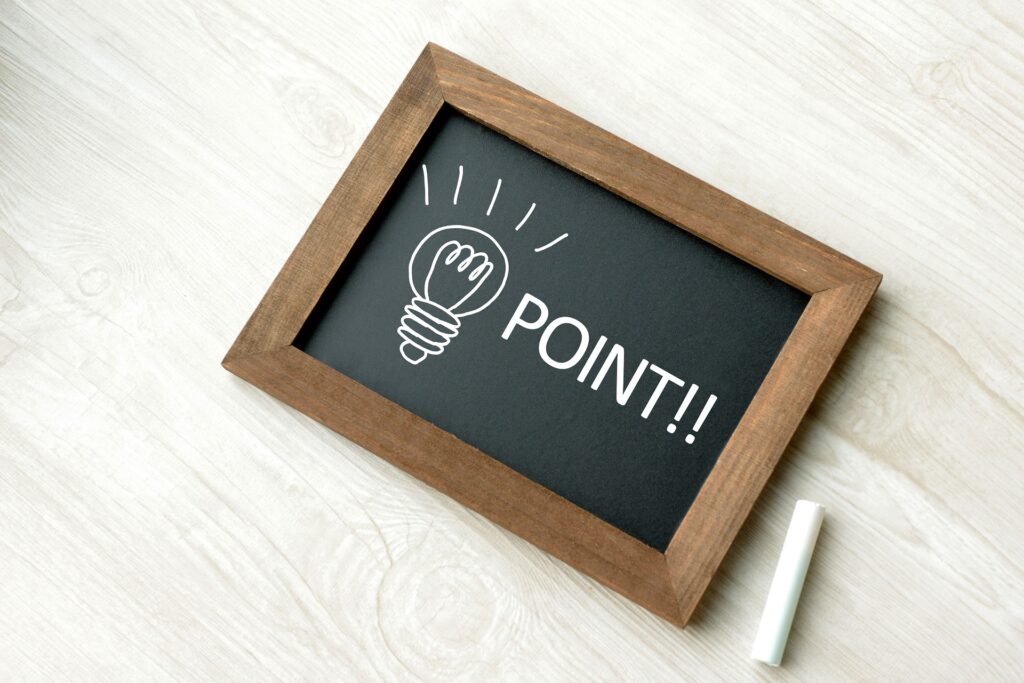
エンゲージメント・サーベイを導入する目的や得られるメリットがわかっていても、正しい方法で活用しないと、期待した効果を得ることはできません。どのような点に注意しながら導入すればいいのかを把握しておくことで、スムーズな導入が実現します。
ここからは、エンゲージメント・サーベイの活用ポイントについて紹介します。
①エンゲージメントスコアとは何か理解する
エンゲージメントスコアとは、エンゲージメントを左右する10~12項目の項目を用いて、従業員の組織に対する愛着心を数値化したものです。
エンゲージメント・サーベイのサービスは多種多様ですが、一般的にはエンゲージメントスコアを用いて、組織と従業員の繋がりが良好かどうかを確認します。
実施方法はアンケートが中心となりますが、「こうすべきである」という絶対的な方法はありません。現在は多くの企業が手探りで導入している段階ですが、従業員の本音や組織の課題を明確化し、リアルタイムで対策が取れる指標として注目されています。
②従業員にエンゲージメント・サーベイを行う目的を伝える
企業が一方的にエンゲージメント・サーベイを実施するだけでは意味がありません。エンゲージメント・サーベイは、従業員本人にどのようなメリットがあるのか、どんな目的で実施するのかなど、丁寧に説明をしましょう。
フィードバックは誰にするのか、結果をどのような形で活用するのか、といったことまで説明して従業員の不安を取り除くことが大切です。
③従業員がエンゲージメント・サーベイに取り組みやすい環境を作る
エンゲージメント・サーベイを行うためには、さまざまな従業員情報を取得しなければなりません。
調査をすることが目的になってしまわぬよう、従業員が主体的に協力できる環境をつくることが大切です。
エンゲージメント・サーベイを実施する際は、ITツールの利用をおすすめします。従業員が長期的に取り組みやすいツールやサービスを導入すれば、従業員への負担を減らすことができ、より満足のいく結果を得られるようになります。
④エンゲージメント・サーベイを継続して行う
エンゲージメント・サーベイは継続してスコアを取り続けないと、満足のいく効果を期待できません。
一度エンゲージメント・サーベイを実施して企業の抱える課題を解決できたとしても、時間が経過すれば新たな課題が浮上し、それに対する改善策が必要となります。
結果を出すには単発で終わらせずに、PDCAをまわしながら半年・1年など長期的に取り組み、組織全体をブラッシュアップしていくことが大切です。
まとめ
組織の隠れた課題や予兆、従業員と組織の関係性を客観的な指標にするには、エンゲージメント・サーベイが必要です。さまざまなエンゲージメント・サーベイがリリースされていますが、従業員を巻き込むには、継続して取り組みやすいツールを選択する必要があります。
サイダスが提供するタレントマネジメントシステム「COMPANY Talent Management」シリーズは、日本企業の高度で複雑な人事制度に最適化され、人的資本マネジメントを統合的にサポートするタレントマネジメントシステムです。組織ごとに異なる人事課題にスピーディに対応できる豊富な機能を備えており、組織力を強化するための分析や、育成のためのプラン作成等、多岐に渡る人材マネジメント運用がこのシステム一つで実現できます。

「COMPANY Talent Management」シリーズの「モチベーションサーベイ」では、世界共通の測定指標「UWES(ユトレヒト・ワーク・エンゲイジメント尺度)」の指標に基づくサーベイによって、従業員のモチベーションを測定。離職リスクが高まっている従業員の早期発見や、人事施策の効果測定を、感覚ではなく、データドリブンに実施できます。


